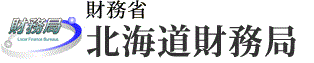平成30年6月1日に『地域活性化支援セミナー』を開催しました 本局融資課・理財課
本セミナーにおいては、地域創生に向けご活躍されている東京農業大学教授 木村俊昭 氏の基調講演のほか、「財投施策説明会」及び「農業融資セミナー」を同時開催しました。
1.日時・場所
平成30年6月1日(金曜日)13時から16時50分
於 札幌第1合同庁舎 2階講堂
2.参加者
3.講演の概要
第1部 基調講演
(1)テーマ・講師
東京農業大学教授 木村 俊昭 氏
【概要】
- 地域創生とは、自分のまちを元気にしようということのみではなく、他のまちと一緒になって強みをより強く、弱みをお互いにカバーし合っていくことで、地域を元気にすることである。
- ストーリー(どのようなまちにするのか、そのためにどのようなことをしていくのか)、台本(誰が、 いつどのように登場させるのか)、脚本(詳細な動き)と指標(ものさし)が必要であり、これらのないまちの地域創生は上手くいかない。また、ストーリーには、目的、目標、使命の明確化が重要となる。
- 何から行ったらいいか分からない時には、自分のまちの産業・歴史・文化をしっかり、もう一度掘り起こすことが必要であり、それを地域の皆さんが一体となり研くことが大切。
- まちの基幹産業(付加価値額 = 多くの人を雇い、給料を払い、税金を納めている産業)への聞き取りを行うなど、徹底的に現場を押さえることが重要(実学・現場重視の視点)。
- 情報共有、役割分担、それぞれの出番を創出、事業構想とその実践。この順番で行うことが重要。
- コトやモノより、人財養成と定着に力を入れることが重要である。まちの全体最適思考を持ったリーダー・キーパーソン、人の話を良く聞きそれをまとめ上げていける人財(増幅型リーダー)が必要となる。
- 木村流の地場産業振興・地域振興は、0歳から14歳を1次、15歳から64歳を2次、65歳から74歳を3次、75歳以上を4次とし、足し算で10次産業振興としている。この皆さんが地域の中で充分に活躍してもらうことをストーリー(台本)に書き込み、ぜひ、行動に移していただきたい。
(2)ご意見・ご感想
- 地域創生には、徹底した現場主義、柔軟な発想と実行力が改めて重要だと感じた。
- 地域のことを知るという事が最初の一歩であると感じた。ビジョンを立てて行動に移していくことが何よりも重要だと思った。
- 地域創生というテーマのみならず、リーダーのあり方、チームのあり方についても多くの気づきを頂いた。

東京農業大学教授 木村俊昭 氏 講演の模様
第2部 財投施策説明会
(1)テーマ・講師
- 「政府系金融機関や官民ファンドによる取組」
- 「農林漁業成長産業化支援機構による取組」
農林漁業成長産業化支援機構
【概要】
政府系金融機関や官民ファンドによる取組
政府系金融機関や官民ファンドは、民業補完を原則としつつ、リスクマネーを供給することにより民間投資を喚起し、民間主導の経済成長が実現することを目的としている。地方にはそういった案件は相応にあるのではないかと考えられ、そうした事業者を支援する。
農林漁業成長産業化支援機構による取組
農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)は、農林漁業の成長産業化を総合的に支援する官民ファンド であり、大きく分けて6次産業化の取組に対する支援と、農業生産関連事業者が行う事業再編・事業参入に対する支援がある。主なメリットは、資金使途の自由度が高い、資金調達力の向上等である。
(2)ご意見・ご感想
- サブファンドの有効活用ができればと考えている。
- どのような支援をするかよりも、事業者が今何を求めているかが大切だと思う。
第3部 農業融資セミナー
(1)テーマ・講師
- 「北海道農業をめぐる事情」
- 「農業融資の着眼点について」
- 「農業信用保証保険制度について」
北海道農業信用基金協会
【概要】
北海道農業をめぐる事情
- 北海道の農業産出額は1兆2,115億円で、全国に占める割合は13.0%(全国1位)。積雪寒冷の厳しい自然条件の下にありながら、広大な耕地を活かし、稲作、畑作、酪農、畜産など、大規模で多様な農業経営が展開。
- 人口減少や高齢化に伴い、国内の市場規模は減少の可能性。一方、世界の農産物マーケットは拡大する可能性。国内外のマーケットの変化にかんがみれば、農林水産業の国際競争力を強化し、輸出産業への成長を目指した強い農林水産業の構築が急務。北海道における農林水産物・食品の輸出額を輸出先国・地域別でみると、アジアが約87%、北米が約7%を占める。
農業融資の着眼点について
農業経営を理解するためには、生産活動が決算書にどう反映するか(業種毎の収支構造)を理解する必要がある。一般的な製造業では、売上高=販売数量×販売単価であるが、農業(畜産業含む)は、売上高=経営規模×単収×単価 (+補助金等)。つまり、単収や単価について、品目や地域等の平均が分かれば、「経営規模からおよその売上高を類推」することができる(特に畜産などの単一経営の場合)。
農業信用保証保険制度について
農業信用保証保険制度は、農業者等の方々の信用力を補完し必要とする資金が円滑に供給されることにより、農業経営の改善、農業の振興に資するようにするために設けられた制度。具体的には、農業者等の方々や地方公共団体等の出資により設立された農業信用基金協会が、融資機関から資金の貸付けを受ける農業者等の方々の債務を保証し、この保証について独立行政法人農林漁業信用基金が行う保証保険により補完する仕組み。
(2)ご意見・ご感想
- 北海道農業の実態と今後の農業事情に関する情報が得られ参考になった。
- 農業の経営分析について、参考になった。
本ページに関するお問い合わせ先
北海道財務局理財部融資課、理財課
電話番号:011‐709‐2311(内線4372)
ファクス番号:011‐746‐0946