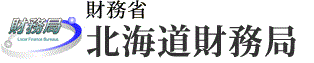「地域連携フォーラム in がんう」を開催しました(平成30年5月17日開催)
※がんう(岩宇)とは、岩内郡(岩内町・共和町)の「岩」、古宇(ふるう)郡(泊村・神恵内村)の「宇」を表す。
1.日時
平成30年5月17日(木曜日)午後1時から午後3時
2.場所
(岩内郡岩内町字高台134番地1)
3.参加機関(順不同)
(1)地方公共団体
岩内町、共和町、泊村、神恵内村、後志総合振興局
(2)経済団体
泊村商工会、神恵内村商工会
(3)金融機関
北海道銀行、北洋銀行、北海道信用金庫、日本政策金融公庫
(4)その他
日本貿易振興機構、小樽商科大学、株式会社キットブルー
4.内容(テーマ)
5.次第
(1)開会挨拶
(2)後援地方公共団体代表挨拶(岩内町長)
(3)議題1 地方公共団体が出資する地域商社株式会社キットブルー支援の取り組みについて
- 課題説明(株式会社キットブルー)
- 金融機関等報告(北海道銀行、北洋銀行、北海道信用金庫、日本政策金融公庫、日本貿易振興機構)
- 意見交換(コーディネーター:小樽商科大学)
(4)議題2 インバウンド需要に対応する電子的資金決済サービスの整備について
- 課題説明(岩内町)
- 金融機関等報告(日本政策金融公庫、北海道銀行、北洋銀行)
- 意見交換(コーディネーター:小樽商科大学)
(5)閉会挨拶

6.名刺交換会

7.主催等
- 主催:北海道財務局小樽出張所
- 後援:岩内町、共和町、泊村、神恵内村
8.議事要旨
- コーディネーター:小樽商科大学 商学部社会情報学科 大津 晶 准教授
- コメンテーター:小樽商科大学大学院商学研究科 アントレプレナーシップ専攻 齋藤 一朗 教授
議事内容及び当日の資料
意見交換はコーディネーターの大津准教授から、各報告機関及びコメンテーターの齋藤教授への質疑応答形式で行われた。
(1)後援地方公共団体代表挨拶(上岡 雄司 岩内町長)要旨
この地域に共通する課題は人口減少や少子高齢化であり、このため基幹産業である農業や水産業、観光業などを活性化することで雇用の場を確保し、地域に新しい人の流れを作り、課題解決を図りたいと考えている。
取り組みを充実、強化していくためには、地方公共団体や事業者単体の取り組みだけでは限界もあり、広域連携や産官学金連携が大変重要だと考える。岩宇地域では4町村が連携して、地域商社の設立による水産業の活性化や観光振興・交流人口の拡大に取り組んでおり、取り組みの推進にあたって、お集まりの皆さまにもお力添えをいただいてこそと思っている次第である。
本フォーラムの開催によって、関係者の皆様が一層の連携を図り、地域経済の活性化につながるよう、ご支援、ご協力をお願い申し上げる。
(2)議題1 地方公共団体が出資する地域商社株式会社キットブルー支援の取り組みについて
1)課題説明
2)金融機関等報告
- 北海道銀行資料(PDF形式:137.62KB)
- 北洋銀行資料(PDF形式:528.26KB)
- 北海道信用金庫資料(PDF形式:88.24KB)
- 日本政策金融公庫資料(PDF形式:904.23KB)
- 日本貿易振興機構資料(PDF形式:1.11MB)
3)意見交換(要旨)
[北海道銀行]
Q:株式会社キットブルーが営業活動する上で重要な点について、貴行が支援する地域商社「北海道総合商事株式会社」の取組事例を交えて教えていただきたい。
A:北海道総合商事株式会社は今年設立3年目。輸出はロシアを中心に、北海道の食材や寒冷地の技術を持ち込み、取扱物量は徐々に増えてきている。しかし、安定した経営を行っていく観点では、取扱事業や販路の拡大がカギとなり、この点株式会社キットブルーも同じ課題を抱えているのではないか。
そこで北海道総合商事株式会社は、輸出だけではなく、ロシアにおける各種プロジェクトにも参画しており、その際に市場調査やコンサルタントを行い、その手数料を収益源としている。困難ではあるが、設立趣旨を逸脱しない範囲で、新事業の展開の検討をすることが株式会社キットブルーにとって重要になってくるのではないか。
[北洋銀行]
Q:海外展開支援において取引先を選定する際に重要となる「信用調査」について、貴行の手法を教えていただきたい。
A:基本的には海外の駐在事務所や提携機関と協力しながら、取引先の登記情報確認、電話や訪問といった現地調査により企業実態を把握しており、更に中国企業に対してはコンプライアンス調査を行い、定期的にモニタリングも行っている。
なお、海外展開におけるリスク軽減策として、NEXI(株式会社日本貿易保険)の貿易保険を勧めている。
[北海道信用金庫]
Q:信金中央金庫と協力した海外販路開拓に向けての支援や情報提供など、具体的な取組みを教えていただきたい。
A:信金中央金庫では、過去には香港で「しんきん食の商談会」を実施しており、香港・インドネシアでの展示会出展のサポートもしている。海外展開に興味のある顧客には、ジェトロ(日本貿易振興機構)などの協力も得ながら、海外で信金会を開催するなどして、必要な情報を提供している。直近では上海信金会を開催しており、ジャカルタやバンコクなどでも開催している。
[日本貿易振興機構]
Q:株式会社キットブルーは機構の提供する各種支援メニューへの参加は可能か。
A:当方の提供する「新輸出大国コンソーシアム」、「道産食品輸出塾」には、株式会社キットブルーが参加する予定となっている。
[小樽商科大学 齋藤教授]
Q:各機関から経営支援の話がある一方、株式会社キットブルーの今後の課題は、経営をマネージメント出来る人材の登用になると思われるが如何か。
A:まず重要なのは、株式会社キットブルーの強みや固有の機能作りといったビジネスコンセプトの確立であり、それから初めて産学金のネットワーク参加や人材登用を考えるべきである。
今は物流よりも、地域の食材発掘や商品開発、あるいはマーケティング活動が中心なので、これに携わる人材をプロパーで抱えられるかが重要である。
Q:今回報告のあった各金融機関等に求められる役割は、何か。
A:株式会社キットブルーのアクションを待つのではなく、自ら関心を抱いて積極的に誘い込んでいく姿勢が必要である。
[小樽商科大学 大津准教授まとめ]
小樽商大では、インターンシップという枠組みの中で、地域に学生が入って、地域のことを学ぶという取組みをしており、株式会社キットブルーの取組みにも参加してもいいのではないか。それが最終的に地域への人材供給に結びつければ、キャリア支援の面でも有意義なものとなる。この産学金の枠組みが地域の振興に結びつけたら幸いである。
(3)議題2 インバウンド需要に対応する電子的資金決済サービスの整備について
1)課題説明
2)金融機関等報告
- 日本政策金融公庫資料(PDF形式:346.46KB)
- 北海道銀行資料1(PDF形式:175.34KB)
- 北海道銀行資料2(PDF形式:176.57KB)
- 北洋銀行資料(PDF形式:1,015.57KB)
3)意見交換(要旨)
[日本政策金融公庫]
Q:報告のあったインバウンドに関するアンケート結果は、日本全国のデータということでよろしいか。また、都市部・北海道地域特有のデータや知見等はお持ちか。
A:日本全国の国民生活事業、中小企業事業のデータなどで、回答数は2300社である。また、北海道等特定の地域を対象としたデータはないが、要望があればデータを作成することも可能である。
(主なアンケート結果)
- お客の中にインバウンドがいる企業の割合は47.0%、売り上げに占めるインバウンドの割合は、7割の企業が「1%未満」とする一方、「11%以上」とする企業も7.7%ある。
- 1カ月当たりのインバウンド数が「50人以上」である企業のうち、独自にウェブサイトを運営している企業の割合は76.9%、更にSNSや動画投稿サイトを利用している企業は47.3%となっている。
[北海道銀行]
Q:貴行はインバウンドプロダクツ2018等で商談のマッチング等をしているが、当イベントに参加が困難な地域へのフォローはされているか。
A:イベントに参加される企業の需要を踏まえると地方開催は難しいが、そういった地域にある自治体や観光協会へは情報を提供し、要望があれば個別のマッチングにより協力していきたい。
[北洋銀行]
Q:貴行の電子決済導入にかかるWi-Fi環境や免税のサポート等について、対象者や規模の基準などはあるか。
A:基準は基本的に設けていない。ご要望があれば対応させていただく。
[小樽商科大学 齋藤教授]
Q:岩宇地域の観光産業全体の環境整備という視点から、電子決済の利便性が、外国人観光客誘致を加速させる有効な経営戦略の手段となり得るか。
A:電子決済を導入したから売上が伸びるという話にはつながりにくく、電子決済はあくまでもインフラ整備の一つという位置付けが必要である。
一方で、岩宇地域の観光産業全体の連携を念頭に置くと、各国の通貨や電子決済に対応する道のほかに、産業的、地域的な連携を見据え、「地域通貨」を導入し、お金を落とす仕組みを見直してみるという方法も考えられる。地域通貨の導入例としては、飛騨信用組合が導入する「さるぼぼコイン」がある。
Q:地域の金融機関に求められる役割について考えを教えていただきたい。
A:地域のお金の流れや需要を把握している地域金融機関の役割は大きい。電子決済を導入するときのサポートもさることながら、その地域にどのような通貨、決済サービスが望ましいのか提案してもらえれば、地方公共団体としても助かるのでなないか。
[小樽商科大学 大津准教授まとめ]
飛騨信用組合の事例のように、金融機関にはこれからも様々なサポートをいただく場面があると考えられる。電子決済の特徴である購買データの蓄積により地域の価値が厚みを増していく仕組みが決済の高度化につながっていくのではないか。
電子決済もすぐには広まらないと思われるが、今年から様々なインバウンド誘客の好機が訪れるというこの岩宇地域は非常に大きな可能性を秘めていると言える。
各金融機関はモデルケースとして、この地域の取組にご協力いただき、大学も社会実験的要素として関わっていきたい。
(4)閉会挨拶(加藤 基 北海道財務局小樽出張所長)要旨
本ページに関するお問い合わせ先
北海道財務局小樽出張所 総務課 電話:0134-23-4103